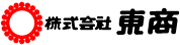苗木を植え付けた際の肥料の与え方について

こんにちは、東商の研究開発センターの村田です。
私たち研究開発センターが、直接お客様のご相談をお受けしたものを
ピックアップしてお届けする園芸相談レター。
今回は「苗木を植え付けた際の肥料の与え方」のお問合せについてお応えします。
果樹の苗木が間もなくご自宅に届くお客様から
「 肥料の与え方に注意点はありますか? 」
というお問い合わせをいただきました。
このときお話しいただいたのは
「苗木を買った際、ホームセンターで12月の寒肥用に
東商の肥料を勧められて購入したのだけれど」
とのこと。
初めて当社の肥料をお使いいただくので、お電話をいただいたご様子でした。
まずおすすめしたのが「植穴」を掘っていただくこと。
果樹苗を植え付けるときは深さ40センチほどの植穴を掘り、
一番底に水はけを良くするため腐葉土を入れます。
その腐葉土と庭土を少し混ぜ、次に待ち肥として肥料50gを入れ、土とよく混ぜます。
それから肥料の入っていない土を入れて苗木を植え付けます。
その後は、苗の芽が春まで動かない(成長しない)ようにしたい ので、
植え付けた後に肥料をまくのは春先まで我慢しましょう。
植穴を作るときにピッタリの肥料は「醗酵油かす」です。
果樹の追肥や寒肥には遅効性の中粒をご用意しています。
また、「醗酵油かす」には花や実付きをよくするアミノ酸が豊富に含まれている ので、
土壌微生物を活性化させ、硬くなりがちな土がふかふかな土へと生まれ変わります。
ふかふかな土とは、土が団粒化して粒の土になる ということを指します。
団粒化とは土の中の微生物の働きにより、土が1㎜程度の小さな団子の粒になり、
その粒がくっつきあっている状態を指します。
団子粒の中には、小さな小部屋がある状態で適度に湿り気が残っている のが特徴。
そのため、周りが乾いてしまっても、湿り気があるので根が枯れにくくなります。
団粒化されている土=水持ちのいい土といえます。
しかし、団粒化は、簡単に作ることはできません。
そのため、腐葉土やピートモス等を土に混ぜます。腐葉土の微生物を増やす効果と、
ピートモスの保水効果で土に水分を持たせ、団粒化を促進させます。
その際、増えた微生物の栄養となるのが「醗酵油かす」です。
栄養がいきわたった微生物が活発化して団粒化が進んでいれば、
微生物や小さな土壌生物が土を耕してくれている証。
有機質の肥料は苗木を育てるだけではなく、土を育てることもできるのです。
ここでひとつお気を付けていただきたいのが、気温の上昇。
近年、暖冬・酷暑と平均気温が上がってきています。
平均気温が高い時は、例年よりも早めに肥料を与えることをお勧めしています。
芽が動き始めたら肥料を与えるタイミング!
芽が動いているということは、土の中で根が伸び始めて栄養を求めているので、
“芽出し肥”を与えましょう。
特に鉢植えは地植えのものと異なり、土の栄養分が限られています。
芽吹きの季節が近づき始めたら、様子を確認するようにしてください。
いずれの場合も一気に与えるのではなく少しずつゆっくりと与えてください。
ゆっくりと葉緑素を作り出すのに必要な養分を届けることで、
薄色をしていた葉が徐々に厚みのある濃い緑をした美しい葉に育っていきます。
追肥をするときは、小さな苗木には100gを4か所に分けて、
大きな木には200gを同じく4か所に分けて、
木の幹を中心に円を描いたときの円周上に与えます。
蒔く場所は枝先の下にくる位置がベスト。
なぜなら、肥料(水分や栄養)を植物体内に取り入れる
根毛(こんもう)を出す根(細根)の伸びている位置が
ちょうど枝先の下あたりに来ているからです。
肥料を与えるときは、少し深めに土を掘って埋めてください。
細根が肥料のある土の深いところまで伸びて待機してくれているので
真夏の乾燥時にダメージを受けにくくなります。
逆に、土の表面付近に浅く張った根だけでは、盛夏の乾燥で表面の土が乾き、
本来届くはずの水分や栄養が届かず木が枯れてしまう(一部の枝が枯れてしまう)
ケースが増えていますので、注意しましょう。
「醗酵油かす」は、果樹はもちろん、花木や花、野菜など、
マルチに使える有機肥料なので安心してお使いいただけます。
ご家庭の様々な植物にもお試しいただければ幸いです。

製造や研究に携わる私たちが皆様の疑問に直接お応えすることで、
少しでも不安を取り除くことができたら本望です。
また、お客様からいただいた貴重なご意見やご質問は、
より良い商品をお届けできるよう、今後の製品開発や改良に活かしてまいります。
これからも、東商の商品の使用方法や、製品についてご不明な点やご質問などございましたら、
お電話やFAX、お手紙などでご相談ください。
東商の商品が、皆様のお花や野菜を育てる喜びの支えになれば幸いです。