家庭菜園の畑の上手な作り方

酷暑はもちろん、長雨など植物にとって厳しい環境が続ているからでしょうか。昨年は家庭菜園があまりうまくできなかった、といったお声を多く頂いています。
前回は酷暑の乗り越え方をお話しましたが、もう一つ注目したい点が、畑の雨上がりの環境がどうなっているか?です。
これから畑を借りる方、もしくは家庭菜園を始める方は、畑にする場所の水の流れを確認しましょう。
雨上がりに水がどこに溜まっているかを確認するのがベストです。
借りる予定のスペースや畑にする場所が、勾配の関係などで水が溜まりやすい場合は注意が必要です。
雨の後1~2日で水が抜けないと、植物の根が酸欠を起こして枯れてしまうからです。
すでに畑で作物を作っていて、雨の後に野菜が枯れてしまった場合も、水はけが悪い場合があります。
でも、なかなか場所を変更することは難しいですよね。
そんな時は、「プチ土地改良」がおすすめです。
1.プチ土地改良をしよう♪
「プチ土地改良」の方法には3つのポイントがあります。
①排水を促す
溝を掘って水を流して水の抜け道をつくる。
②高さを上げる
盛り土をしましょう。ブロックや板で30cmの囲いを作ると、周囲より高くすることができます。
③土自体の改良をする
根に空気(酸素)が入りやすいように、空間を作りましょう。
砂質の土や粘土が多い土は、耕しても粒の土がこわれ、しめった土になりやすいものです。
そこで、土の構造を、固形の部分と空気の部分、水の部分と、土の三層分布の空気の部分が適切になるように改良するのです。
空気の層を作るには、腐葉土やピートモス、もみ殻、藁など有機物(もしくは、これらを原料にした堆肥など)を使います。
無機物(パーライトや軽石など)を入れて、空気の層をつくる土づくりをします。
また、水が溜まりやすい場所でも、高さがあれば畑の畝(うね:根が育っている場所)に水がたまることはありません。
水はけも良くなるので、根の張りも促進され、根腐れなど病気の予防になります。
植え付けは、土を耕し、肥料を入れて平らにならしたら1週間程度おいて、土に肥料をなじませます。
余談ですが、畑を始めるときには、おおよそ畳何枚分の広さになるかを把握しておきましょう。
畳1枚で1.5平米になりますので、肥料を入れる際の分量の目安になります。
※寸法を測るために、いつも使う道具に目盛りを振りましょう。
鍬の柄に、50㎝と1メートル、長めの支柱:おおよそ180㎝(一間:いっけん)に印をつけて長―い物差しを作っておくと役に立ちます。
1週間が過ぎたら、いよいよ植え付けです♪
土作りに適した肥料
1㎡あたり200g
1㎡あたり200g

1㎡あたり300g
2.畑に苗や種を植え付ける前後にしよう♪
新しく野菜の苗の植え付けや種まきのときは、まず畝を作りましょう。
畝の高さは水はけの善し悪しによって決めます。
もともと水はけが悪い場所にある畑はもちろん、昨年の梅雨時などに根腐れを起こしてしまった場合は、水はけが悪いことが原因の一つ。
その場合は、20cmくらいの高畝を作りましょう。
畝を作ることによって、根元に水が溜まるのを防ぐことができるので、長雨が続いても酸欠を予防することができます。
畝が出来たら植穴を掘ります。
植穴の間隔は、野菜の種類によって異なるので、あらかじめ調べておきます。位置が決まったらシャベルで植穴を掘ります。
※ここでポイント!
掘り終わった植穴には、あらかじめ水をためるつもりで水を注ぎます。
まるで、お湯が抜けきったコーヒーフィルターのような状態になっていたらOK。
植穴の下に水がキープされた状態になります。
定植した苗の根は、周りの水しか吸いません。
あっという間に根の周りの水を吸い取り、土の中が乾いてしおれてしまうのを防ぐためです。
しっかり地中深くまで水を入れれば、植物の周りに水が吸い込まれていく縦の線ができているような状態になります。
縦の線に沿って地表から吸い込んだ水がゆっくり根から吸い込まれて循環していきますので、水切れを起こす心配が減少します。
夏以外でも、春先など風が強い季節は地表も苗も乾燥しがち。
苗の定植の時、あらかじめ植穴に水を注いで置く作業は、苗を水切れから守るためにも大切な作業なので、必ず行ってください。
水を入れた後の植穴には、鉢に植えてあった土の高さと、植え付けたときの土の高さが少し下になるように植え付けます。
苗のの土が、植えた土の表面より飛び出したりしていると、水やりを続けるうちに、上根が土から出てしまい枯れてしまいますので気を付けましょう。
植え付けた苗の本葉がピーンとするまでの数日間は、気にかけておいてください。
3.植え付け後の支柱の立て方って?
植え付けたばかりの苗は根がしっかり張れていないため、頭でっかちな状態です。
ひとたび強い風が吹くと倒れてしまう恐れがあるので、斜めに40cmくらいの仮支柱を立ててあげることが大切です。
支柱の長さは、地面に刺すので40㎝くらいあると良いですね。
苗と支柱は麻ひもで8の字を描くように緩く結びます。
仮支柱は苗が完全に根つき、ツルや側枝が伸び始めたら本支柱にかえましょう。

仮支柱を刺した後は、風や寒さから守るために苗の周りに4本の支柱を四角形になるように刺します。
そこへビニール袋の底を抜いて、筒状にしたものをかけてやります。
ちょうど行灯みたいな形になると思います。
行灯型の囲いをつくることで、風の影響で葉から水蒸気が逃げる速度を遅らせることができます。
また、風は一方向から吹くのではなく、多方面からまわるように吹き付けるので、苗がよれてダメージを受けることも防ぐことができます。
行灯型の囲いは、植え付けから2、3週間程度の期間はつけたままにしておいてください。
葉が成長し、袋につきはじめると、根が横に広がった合図です。このタイミングで取り外しましょう。
ここまで、畑の作り方から植え付けまでお話をしてきました。
最初は、どなたも見よう見まねでスタートします。
貸農園の場合は、お隣の方などと情報交換をすると色々なアドバイスをもらえるかもしれません。
土いじりはストレス解消にもつながりますので、畑のある生活を楽しんでくださいね♪
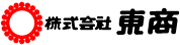






%E6%9C%89%E6%A9%9F100%EF%BC%85%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%81%AE%E8%82%A5%E6%96%99650g.jpg)