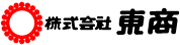連作障害について
■Q1
プランターで使った土の再生材(もっとつかえーる・等)について
酸性になった土のpH調整、不足した栄養分の補充等と書かれていますが
連作障害の除去効果は無いのでしょうか。
■A1
連作障害が発生する原因はいくつかあります。
「もっとつかえ~る」は有害線虫や土壌病害虫への対策には対応しておりませんが
土の有効菌(13属80種類の微生物群)を配合しており
「土壌有効微生物の不均衡」に起因する連作障害の軽減に効果があります。
堆肥や腐葉土と併用していただくことで、土壌中の微生物相の改善がより促進されます。
■Q2
連作を避けるに輪作を推奨されていますが、
春植え(ウリ科=胡瓜)・夏収穫後、秋植え(アガサ科=ほうれん草)・冬収穫は、理解できますが
ナスは、夏収穫と秋ナス(秋収穫)が有りますが、その後にユリ科の玉ねぎの植付けでOKですか。
■A2
ナスの夏収穫・秋収穫の後に、タマネギを植え付けることは可能です。
ナス科(ナス、トマト、ピーマン)の後にユリ科(玉ねぎ、ネギ)を植えることで
輪作が成立しています。
■Q3
輪作は、ナス科⇒ユリ科、翌年春にウリ科⇒アガサ科、翌々年にナス科に戻って
と言うような繰り返しはOKでしょうか。
■A3
ナス科の作物は同じ場所での栽培を3~4年空けるのが望ましいとされています。
そのため、4年目以降に再びナス科を栽培するサイクルをおすすめいたします。
例えば、以下のように輪作を行なってみてはいかがでしょうか。
1年目 ナス科⇒ユリ科
2年目 ウリ科⇒アカザ科
3年目 マメ科⇒アブラナ科
4年目 ナス科⇒ユリ科
■Q4
連作障害を無くすには、3年~4年との事ですが、これは、その間何も作らない。
土地や土の放置と言う事でしょうか。
■A4
植物を植えずに土を放置しておくと、土は次第に荒れていきます。植物が生えることで根の周囲に多くの微生物や小動物が集まり、生物相が発達して地力を高めることができます。
反対に作物を育てずに除草だけを繰り返していると、やがて砂漠のようなやせた土となってしまいます。
休耕する場合は、堆肥や安価な鶏ふんなど、入手しやすい有機素材を組み合わせて
土づくりをしておくと良いでしょう。
また、季節に合わせた『緑肥』を利用されてはいかがでしょうか。イネ科やマメ科などの種子が市販されており、次に育てる作物の科や耐暑性に応じて選ぶことができます。
緑肥は土壌改良だけではなく、夏草雑草の侵入を防ぐこともできる良い方法です。
輪作のほか、害虫予防に効果があるコンパニオンプランツや
線虫の予防に役立つ植物(マリーゴールドなど)の組み合わせもおすすめです。
また、深耕する、畝の高さを変える、雨が続くときの排水性を改善することも
物理的な土壌環境を変える要素となり、病害虫の発生を抑える効果が期待できます。
【補足】
下記の野菜は、科の分類が以前と変更になっていますので、よろしければご参考にしてください。
・玉ねぎ:「ユリ科」⇒現在は「ヒガンバナ科」に分類されています。
・ほうれん草:「アカザ科」⇒現在は「ヒユ科」に分類されています。